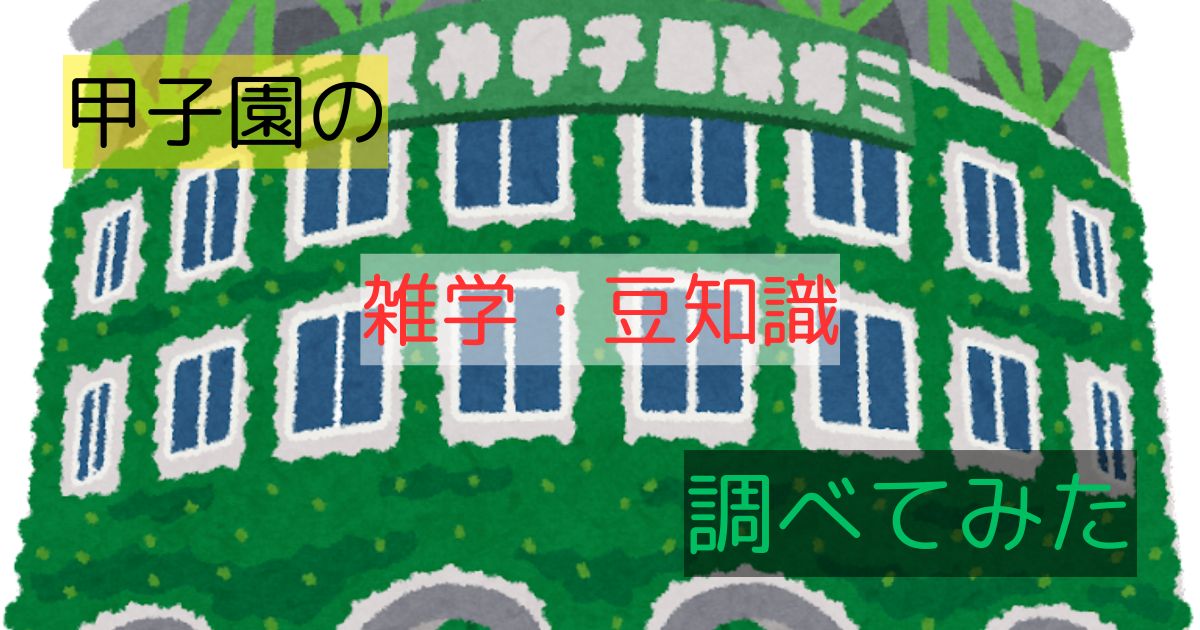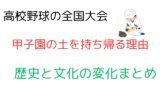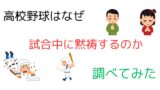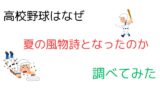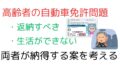甲子園といえば、高校野球や阪神タイガースの聖地として知られています。しかし、その舞台裏にはあまり知られていない歴史やエピソードが数多く存在します。
本記事では、甲子園にまつわる雑学・豆知識をたっぷり紹介し、野球ファンなら思わず誰かに話したくなるような裏話をまとめました。
甲子園は川の上に建っていた?
現在の甲子園球場が建つ場所は、かつて「枝川」という川が流れていました。埋め立てて建設されたため、地盤は砂質で水はけが良く、大雨のあとでも比較的早くグラウンドコンディションが回復します。
夏の甲子園大会が予定通り進行できるのは、この立地条件のおかげとも言われています。
「甲子園」という名前の由来
1924年(大正13年)、全国中等学校優勝野球大会(現在の全国高校野球選手権大会)のために球場が完成しました。
その年はちょうど干支の「甲子(きのえね)」にあたる年だったことから、「甲子園」と名付けられました。単なる地名ではなく、縁起を担いだ名称なのです。
プロ野球よりも高校野球が先
甲子園は阪神タイガースの本拠地として有名ですが、実は高校野球のために建設された球場です。
プロ野球が誕生するのはその後で、甲子園がいかに高校野球と深い結びつきを持っているかがわかります。
ラッキーゾーンの思い出
かつて甲子園には外野フェンスの内側に「ラッキーゾーン」と呼ばれる柵が設置されていました。これによりホームランが出やすくなり、数々の名勝負を生み出しました。
しかしプロ野球では打撃優位になりすぎたため、1992年に撤去されました。今でも「ラッキーゾーンがあった時代の方が面白かった」というファンも少なくありません。
甲子園の土を持ち帰る文化
敗れた球児が甲子園の土を持ち帰るシーンは夏の風物詩として定着しています。この習慣は1940年代頃から自然に始まったもので、現在では持ち帰り用の袋まで用意されています。
単なる思い出ではなく、「再挑戦」や「仲間との絆」を象徴する文化として広まっています。
収容人数の移り変わり
甲子園は開場当初、約55,000人以上を収容できました。しかし安全性や観戦環境の改善を重視し、座席の広さや施設改修を経て、現在は47,000人ほどとなっています。
それでも日本最大級の球場であることに変わりはありません。
ナイター照明導入は意外に遅い
プロ野球のナイター試合が一般化していたにも関わらず、甲子園に照明塔が設置されたのは1984年。周辺住民への配慮や景観の問題から導入が遅れたのです。
今では名物の「六本の照明塔」も、当時は賛否を呼びました。
隠れエピソード・豆知識
銅像の向きが変わったことがある
甲子園前には「球児の像」が設置されていますが、かつては正面玄関の方を向いていました。その後、より多くの来場者に見てもらえるよう配置換えが行われています。
阪神園芸の職人芸
甲子園のグラウンド整備を担う「阪神園芸」の技術は世界的に有名です。雨でぬかるんだグラウンドを短時間で回復させる姿は「魔法の整備」と称され、SNSでも毎年話題になります。
夏の甲子園は“入道雲”も名物
アルプススタンドと外野スタンドの向こうにそびえる入道雲は、夏の甲子園ならではの光景。選手たちの奮闘と相まって、観戦者の記憶に強く残ります。
実はコウノトリのふるさとに近い
甲子園球場がある兵庫県西宮市は、豊かな自然に恵まれたエリア。かつては近隣でコウノトリが見られる地域であり、「甲子園」という名前に「縁起の良さ」を感じる人もいます。
FAQ
- Q甲子園はなぜ水はけが良いのですか?
- A
球場が建設される前に「枝川」という川が流れており、砂質の地盤が水はけを良くしているためです。
- Qラッキーゾーンが撤去されたのはいつですか?
- A
1992年に撤去されました。理由はプロ野球でホームランが出やすくなりすぎたためです。
- Q甲子園の土は誰でも持ち帰れますか?
- A
一般観客は持ち帰れません。高校球児のみに配布される専用の袋があります。
- Qナイター照明はいつから設置されましたか?
- A
1984年からです。周辺環境への配慮から導入が遅れました。
- Q阪神園芸が注目される理由は?
- A
短時間でグラウンドを整備する技術が世界的に評価され、「甲子園の名脇役」とも呼ばれています。
おすすめ関連記事
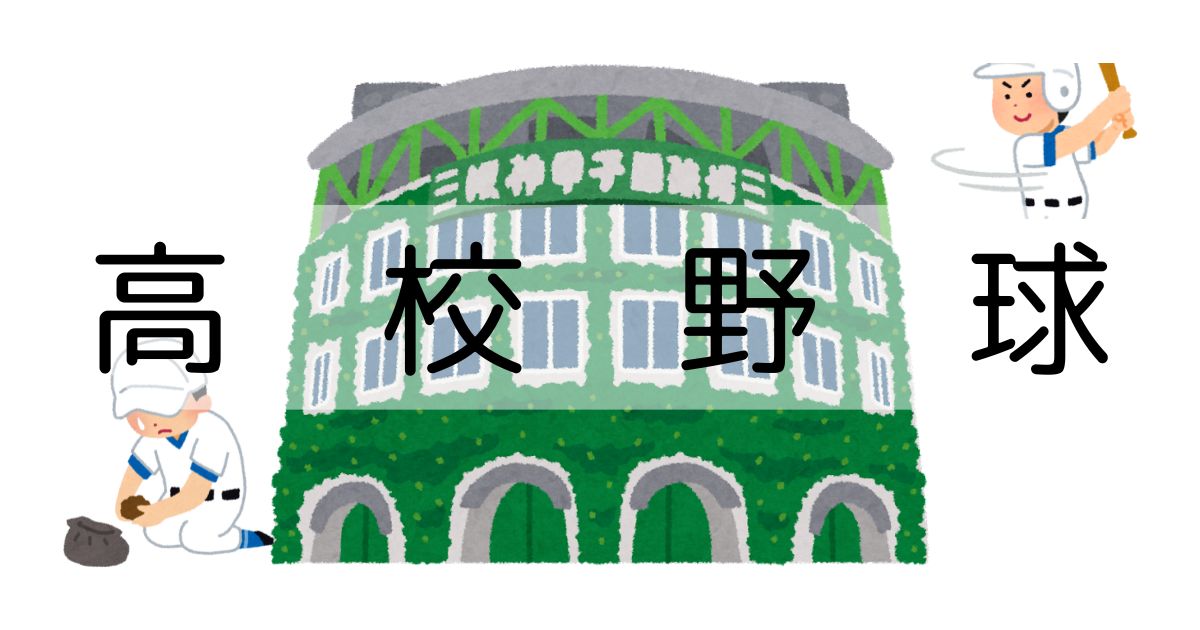
高校野球に関するタグです。