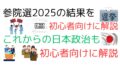選挙のたびに話題になる「ネット投票」。スマホ1つで投票できれば便利なのに……と思う人も多いでしょう。しかし、日本では今もなお「紙に書いて投票する」というスタイルが続いています。
この記事では、
- なぜネット投票は導入されていないのか?
- 「半ネット投票」はダメなのか?
- 電子的な投票を行うメリット・デメリット
と+αで
- 「鉛筆で書くと書き換えられる」といった誤解
について、わかりやすく解説します。
ネット投票ができない理由(デメリット)
投票の「秘密」が守れない
自宅でスマホから投票できるとなると、誰かに見られていたり、指示されたりする可能性があります。これでは「本人の自由意思で投票した」とは言い切れません。
たとえば、家族や知人に強制されたり、金銭で買収されたりすることも理論上可能です。これでは公平な選挙が成り立たなくなってしまいます。
なりすましのリスク
マイナンバーカードを使った認証を導入しても、本人になりすまして誰かが投票する危険性は完全には消せません。ネット上での「本人性の担保」はとても難しい課題です。
サイバー攻撃の危険性
選挙は国家の根幹です。ネット投票にしてしまうと、外部からのハッキングやデータ改ざんなどが大問題になります。実際に海外では、選挙システムが攻撃された事例もあります。
ITリテラシー格差
高齢者やネットが苦手な人にとって、スマホ等の電子機器で投票するのはハードルが高いです。全世代にとって平等な投票環境を確保するという観点からも、慎重にならざるを得ません。
「半ネット投票」という現実的な方法
しかし、「やらない理由」だけを探していては、何も進歩しません。とはいっても、「選挙の公平性を保つ」ことは非常に重要なことでもあります。
なので、完全に自宅から投票するのではなく、投票所に設置された端末で投票する方式、つまり「半ネット投票」について考えたいと思います。
どうしても、選挙の投票に対して利便性の向上を図らないと投票率の向上も難しいものがあると思います。なので、ネット投票に向けた第一歩として「半ネット投票」の考え方を発信します。
もちろん、何事にも「メリット」「デメリット」は存在します。なので、現状の私が考える「メリット」「デメリット」については後述いたします。
※「半ネット投票」という言葉は筆者による造語です。
【ちょっと脱線】愛媛県新居浜市の実証実験(2020年)
「半ネット投票」とは異なるのですが、現行の「投票所に行く」という常識を進化させる為の実証実験が行われていたので、「こんなのもあるよ」という意味合いでご紹介します。
これは、正式な選挙ではなく「滝の宮公園にあったらいいね!遊具選抜選挙」という模擬投票体験のイベントのようです。
どんな内容であったかというと
- 車を使った移動式投票所
というものです。自宅前まで来てくれるという訳では無いと思うのですが、「投票所まで遠い」方だと
- 選挙、面倒臭いし、まっいっか
と投票率が下がる要因になります。しかし、「学校」や「ホール」が近くに無いとどうしても投票所は遠くなりがちです。
そんな中、「車が停められる広場等でも投票所として扱う」ことができれば、今以上に多くの投票所を設けることが可能になると思います。
これは、「コロナ禍」に行われた「密を避ける為」を目的に行われたそうですが、投票の利便性向上と公平性が保てるのであれば、この「移動式投票所」という考えもアリかなと思いました。

半ネット投票のメリット
開票作業が早く終わる
紙を開いて、人力で数える必要がなくなるため、開票が一瞬で終わります。人件費も削減できるでしょう。
票の改ざんリスクが減る
紙の投票用紙のすり替えや、意図的な無効票処理などの不正が発生しにくくなります。
無効票の減少
タブレットでの選択式にすることで、名前の書き間違いや白票といった「無効票」が減ることが期待されます。
視覚障がい者などへの配慮が可能
音声読み上げや拡大表示など、機械ならではのアクセシビリティ支援も行いやすくなります。
半ネット投票のデメリット
設備コストがかかる
各投票所に端末を設置し、保守・更新していくには相当なコストがかかります。特に財源に限りのある自治体にとっては導入のハードルが高いと考えられます。
機器トラブルのリスク
選挙当日にシステム障害が発生した場合、対応が遅れると投票そのものが混乱しかねません。なので、システムの「片方」がダメになっても「もう片方」が正常なら大丈夫という状況を作り出す必要があります。
システム的には「可用性」が求められます。
システムの信頼性確保が必要
「誰が・いつ・どこで・何に投票したか」が不正に追跡できてしまうようでは、秘密投票の原則が崩れてしまいます。技術面での信頼性だけでなく、有権者からの心理的な信頼も得ることが不可欠です。
あわせて、不正アクセスの対策についても議論する必要が出てきます。
システム的には「機密性と完全性」が求められます。
【余談1】よくある誤解:鉛筆で書くと書き換えられる?
SNSなどではよく、「投票用紙に鉛筆で書くのは危険。書き換えられる」という声を見かけます。
しかしこれはほとんど誤解に近いと言えます。
鉛筆を使う理由
- 投票用紙は特殊な紙(ユポ紙)
- 通常のコピー用紙とは異なり、鉛筆が最も適している。
- ボールペンの方が消しやすい
- ユポ紙は油分に弱いため、インクが定着しにくく、ボールペンの方が実は「消しやすい」こともある。
投票所では投票箱の管理が厳格にされており、不正な書き換えができる環境ではありません。
また、開票作業についても裁判と同じく公開されているため、開票作業時も書き換えは困難といえます。(鉛筆以外で書かれた投票用紙を袖などで消して無効票とすることは、、、?)
【余談2】投票の「公開性」とは?誰でも見に行けるの?
投票や開票に関して、選挙管理委員会は「公開性」を重視しています。
特に開票作業は原則として一般に公開されており、誰でも見学可能です。
実際に見に行くには?
- 地元の市区町村の選挙管理委員会のHPで「開票所」と「時間」をチェック
- 入場制限がある場合もあるので、事前に確認を
※撮影などは禁止されていることが多いため、マナーには注意しましょう。
まとめ:完全ネット投票は難しいが、「電子化」は第一歩
現時点では、自宅からのネット投票は公平性やセキュリティの観点から現実的ではありません。しかし、「投票所に設置した専用端末での電子投票」であれば、メリットも多く、現実的なステップとして検討される価値があります。
将来の選挙制度をより便利に、公正にしていくためにも、「半ネット投票」の可能性に今一度注目してみてはいかがでしょうか。
よくある質問(FAQ)
- Qなぜ海外ではネット投票ができる国があるの?
- A
エストニアなど一部の国では導入されていますが、国民ID制度の徹底、ITリテラシーの高さ、小規模人口などの要因が大きく、日本とは条件が異なります。
- Qブロックチェーン技術を使えば安全じゃないの?
- A
技術的には改ざんを防げる仕組みですが、「誰が誰に投票したかを見られないようにする」という投票の匿名性との両立が難しいのが課題です。
- Q今後すぐに半ネット投票が始まる可能性はある?
- A
現時点では法制度の整備や費用の問題もあり、すぐに全国展開される見込みは薄いですが、将来的に再検討される余地はあります。