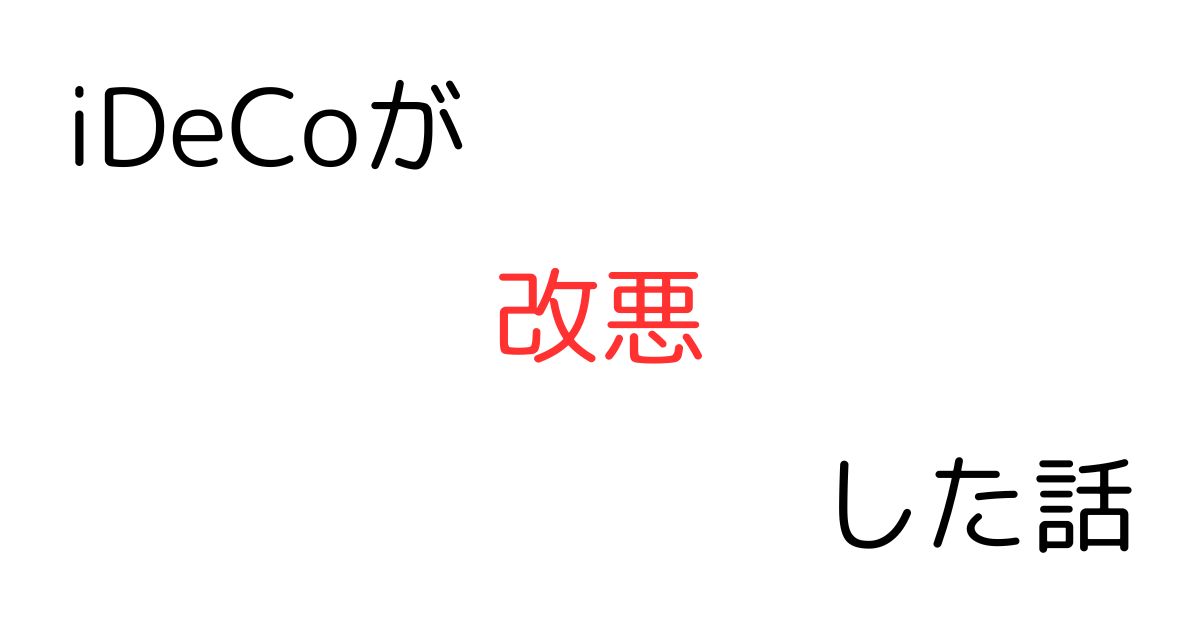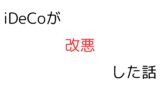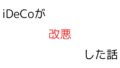みなさま、こんにちは。当記事では、「iDeCoの改善点」と「NISAの方が良いの?」について触れていきます。最後には
- iDeCo始めるべき?
- 既にiDeCo加入しているがどうする?
- 結局どんな人がiDeCoに加入するべき?
について触れていますので、是非最後だけでもご覧ください。また、iDeCoの改悪点については前編で触れてますので、よければそちらもご覧ください。
iDeCoの改善点
まず、2024年12月に改善された点は次の2点です。
- 事業主の証明書廃止
- 拠出限度額の引き上げ
事業主の証明書廃止について
2024年11月まではiDeCoに加入する際、第2号被保険者(会社員・公務員)に該当する方は事業主の証明書を提出する必要がありました。この事業主の証明書は自身で作成することができず、勤め先に作成を依頼する必要があり、iDeCo加入の重い足枷になっていました。
しかし、2024年12月以降は事業主の証明書が不要になり第2号被保険者に該当する方でも自身の手続きだけで加入が可能になりました。
拠出限度額の引き上げについて
こちらも2024年12月に拠出限度額が引き上げられましたが、この時の引き上げは第2号被保険者を対象としたものです。しかし、現在も更なる引き上げが検討されています。
過去(〜2024年11月)、現在(2024年12月)、将来の限度額引き上げに関して以下の表に表してみます。
| 加入者 | 拠出限度額(月額) | |||
|---|---|---|---|---|
| 過去 | 現在 | 未来 | ||
| 第1号被保険者 | 6.8万円 | 6.8万円 | 7.5万円 | |
| 第2号被保険者 | 企業年金なし | 2.3万円 | 2.3万円 | 6.2万円 |
| DCのみ加入 | 2.0万円(※1) | 2.0万円(※1) | 6.2万円(※3) | |
| DC/DB共に加入 | 1.2万円(※2) | 2.0万円(※1) | 6.2万円(※3) | |
| DBのみ加入 | 1.2万円 | 2.0万円(※1) | 6.2万円(※3) | |
| 公務員 | 1.2万円 | 2.0万円(※1) | 6.2万円(※3) | |
| 第3号被保険者 | 2.3万円 | 2.3万円 | 2.3万円 | |
(※2)企業型DCの拠出合計額が1.55万円を上回る場合、「2.75万円 – 企業型DCの拠出額」がiDeCoの拠出限度額となる。
(※3)「6.2万円 – 企業型DC/企業型DBの拠出額」がiDeCoの拠出限度額となる。
iDeCoの拠出上限額については上表の通りです。特徴としては、
- DBに加入している会社員と公務員は既に恩恵を受けており、
更なる恩恵が受けられるかもしれない - 将来的には、第3号被保険者を除き全員に恩恵があるかもしれない
といったところでしょうか。しかし、正直どうでしょう。私はここまで記事を書いてこんなことを思いました。「これって改善点って言える?」と。前編のまとめ部分でも書きましたが、出口部分(取り崩し時)で大きく課税する改正(改悪)が今後も起き得るなら、拠出額は抑えるべきなのでは?
- 5年以上かつ60歳まで資金拘束される
- 未来のルールは誰にもわからない(取り崩し時に改悪される恐れあり)
この2点だけでも、iDeCoの拠出額を減らす或いはiDeCoを始めない理由になり得ると考えますが皆さんはどのように思われますでしょうか。
NISAの方が良いの?
私の個人的感想にすぎないですが、結論NISAの方が良いと考えます。理由としては次の3点です。
- 非課税枠が1,800万円も存在する
- いつでも売却(現金化)できる
- 売却した分は元本部分のみ翌年に非課税枠が復活する
特に注目すべきは「2」です。NISAはiDeCoと異なりいつでも売却することができます。なので、NISAが改悪するなら現金化して逃げることも可能です。iDeCoでは資金拘束されるため逃げることができません。(iDeCoもスイッチング(別の商品に乗り換える)は可能です。)
簡単ではありますが、NISAとiDeCoの特徴を表にしてみます。
| NISA | iDeCo | |
|---|---|---|
| 入口 (投資) | 特になし | 全額所得控除となる |
| 中間 (運用) | 運用益(配当含)は非課税 (外国株は税金が掛かる) | 同左 但し、iDeCoに配当は存在しない |
| 出口 (売却) | いつでも可能 | 60歳以上かつ5年以上の加入が必要 |
| 各種所得税は0円 | 元本含めて税金が掛かる。一時受取時は”退職所得”。年金受取時は”雑所得”。 | |
| 投資限度額 | 総額1,800万円 積立:1,800万円 成長:1,200万円 年間360万円 積立:120万円 成長:240万円 | 総額限度は存在しない。月額限度額は、上述してある「拠出限度額の引き上げについて」を参照 |
| 商品数 | 金融庁が定めた条件を満たす投資信託、上場株式など | 証券会社によって異なるが、35本程度 |
| スイッチング | 可(但し、売却後すぐに非課税枠が復活する訳ではないので注意が必要) | 可 |
老後資金を準備するだけならNISAの非課税枠1,800万円だけでも多くの人にとっては十分です。なんなら、多くの方は非課税枠1,800万円を消化しきれないと思います。
また、NISAで勘違いされている方がいらっしゃるのですが、1,800万円の枠全てを積立で消化することも可能です。成長枠の上限が1,200万円だからといって「成長枠も活かさないと」と無理をする必要はありません。
NISAを利用して資産形成をする場合の最終的な資産額も以下表にまとめましたので、是非参考にしてみてください。老後に必要な資産額は三者三様で答えられないですが、目標が定まっていない多くの人は緑色(30,000,000円〜49,999,999円)周辺を目標にすれば良いかなと思います。
ご自身で積立額や利回り、積立額や利回りを増減したシミュレーションを行いたい場合は以下の記事をご利用ください。
- 5,000,000円未満:灰色
- 10,000,000円以上:黄緑色
- 30,000,000円以上:緑色
- 50,000,000円以上:オレンジ色
- 100,000,000円以上:赤色
シミュレーションはあくまで参考レベルです。実際には暴落暴騰を繰り返すので運用期間が短ければ短いほどシミュレーション結果から乖離し易くなります。
NISAで月1万円を投資する場合
| 積立年数 | 元本 | 利回り(3%) | 利回り(5%) | 利回り(7%) |
|---|---|---|---|---|
| 5年 | 600,000 | 648,082 | 682,900 | 720,103 |
| 10年 | 1,200,000 | 1,400,907 | 1,559,297 | 1,740,945 |
| 15年 | 1,800,000 | 2,275,402 | 2,684,030 | 3,188,117 |
| 20年 | 2,400,000 | 3,291,232 | 4,127,464 | 5,239,657 |
| 25年 | 3,000,000 | 4,471,234 | 5,979,910 | 8,147,977 |
| 30年 | 3,600,000 | 5,841,940 | 8,357,262 | 12,270,880 |
| 35年 | 4,200,000 | 7,434,181 | 11,408,258 | 18,115,611 |
| 40年 | 4,800,000 | 9,283,754 | 15,323,783 | 26,401,247 |
NISAで月3万円を投資する場合
| 積立年数 | 元本 | 利回り(3%) | 利回り(5%) | 利回り(7%) |
|---|---|---|---|---|
| 5年 | 1,800,000 | 1,944,246 | 2,048,684 | 2,160,317 |
| 10年 | 3,600,000 | 4,202,721 | 4,677,879 | 5,222,835 |
| 15年 | 5,400,000 | 6,826,201 | 8,052,077 | 9,564,339 |
| 20年 | 7,200,000 | 9,873,682 | 12,382,385 | 15,718,962 |
| 25年 | 9,00,000 | 13,413,686 | 17,939,726 | 24,443,913 |
| 30年 | 10,800,000 | 17,525,809 | 25,071,787 | 36,812,619 |
| 35年 | 12,600,000 | 22,302,521 | 34,224,779 | 54,346,811 |
| 40年 | 14,400,000 | 27,851,235 | 45,971,354 | 79,203,727 |
NISAで月5万円を投資する場合
| 積立年数 | 元本 | 利回り(3%) | 利回り(5%) | 利回り(7%) |
|---|---|---|---|---|
| 5年 | 3,000,000 | 3,240,417 | 3,414,483 | 3,600,526 |
| 10年 | 6,000,000 | 7,004,540 | 7,796,477 | 8,704,724 |
| 15年 | 9,000,000 | 11,377,006 | 13,420,153 | 15,940,563 |
| 20年 | 12,000,000 | 16,456,138 | 20,637,338 | 26,198,271 |
| 25年 | 15,000,000 | 22,356,143 | 29,899,580 | 40,739,861 |
| 30年 | 18,000,000 | 29,209,684 | 41,786,355 | 61,354,382 |
| 35年 | 18,000,000 | 33,930,458 | 53,626,883 | 86,977,528 |
| 40年 | 18,000,000 | 39,414,194 | 68,822,528 | 123,301,542 |
NISAで月10万円を投資する場合
| 積立年数 | 元本 | 利回り(3%) | 利回り(5%) | 利回り(7%) |
|---|---|---|---|---|
| 5年 | 6,000,000 | 6,480,833 | 6,828,939 | 7,201,055 |
| 10年 | 12,000,000 | 14,009,076 | 15,592,928 | 17,409,449 |
| 15年 | 18,000,000 | 22,754,010 | 26,840,262 | 31,881,125 |
| 20年 | 18,000,000 | 26,431,442 | 34,445,682 | 45,195,483 |
| 25年 | 18,000,000 | 30,703,204 | 44,206,161 | 64,070,259 |
| 30年 | 18,000,000 | 35,665,355 | 56,732,359 | 90,827,617 |
| 35年 | 18,000,000 | 41,429,473 | 72,807,968 | 128,759,525 |
| 40年 | 18,000,000 | 48,125,168 | 93,438,735 | 182,532,755 |
過去のS&P500のリターンを軸にシミュレーションした場合
2025年2月時点の話ではありますが、投資信託等で人気のS&P500の過去のリターンは次のとおりです。(配当を再投資した場合)
| 期間 | リターン(%) |
|---|---|
| 1年 | 34.8 |
| 3年 | 19.6 |
| 5年 | 22.4 |
| 10年 | 15.8 |
| 15年 | 17.7 |
| 20年 | 12.6 |
| 30年 | 12.5 |
もちろん、未来は誰にもわかりませんが今後もこのくらいの利回りで運用できたと仮定し遊び半分でシミュレーションをしてみましょう。当記事では、利回り12%でシミュレーションをしてみます。
| 積立年数 | 毎月1万円 | 毎月3万円 | 毎月5万円 | 毎月10万円 |
|---|---|---|---|---|
| 5年 | 824,864 | 2,474,591 | 4,124,313 | 8,248,638 |
| 10年 | 2,323,391 | 6,970,175 | 11,616,943 | 23,233,908 |
| 15年 | 5,045,756 | 15,137,283 | 25,228,779 | 50,457,601 |
| 20年 | 9,991,476 | 29,974,446 | 49,957,362 | 91,666,161 |
| 25年 | 18,976,347 | 56,929,069 | 94,881,689 | 166,529,609 |
| 30年 | 35,299,131 | 105,897,445 | 176,495,564 | 302,533,789 |
| 35年 | 64,952,677 | 194,858,132 | 320,638,910 | 549,612,137 |
| 40年 | 118,824,173 | 356,472,713 | 582,503,649 | 998,478,560 |
もし、、、の話ですが今後もこの位のリターンがあれば月1万円でも30歳〜60歳の期間だけで3,000万円を上回ることができます。月5万円でも40歳〜60歳の期間で4,000万円です。
改めての結論
NISAの1,800万円の枠内でも十分資産形成が可能です。なので、節税効果があるからという理由だけでiDeCoを急ぐ事はないです。
NISAすら使っていない方は、まずNISAから始めることを強くお勧めします。その上で、余剰資金があり所得税もそれなりに納めているならiDeCoを始めてみるのも良いかと考えます。
まとめ
これまでiDeCoを軸に触れてきましたがいかがでしたでしょうか。まだiDeCoについて触れられていない点や、iDeCoに限らず書きたい事は山ほどあるのですが書きすぎても何が言いたいのかまとまらなくなるので、この位にしておこうと思います。そして、前半で触れた3つの疑問について私なりの答えは次のとおりです。
- QiDeCo始めるべき?
- A
NISAだけで十分であると考えます。
- Q既にiDeCo加入しているがどうする?
- A
改悪されたとは言え、取り崩し時の恩恵はまだ大きいので無理に拠出を止める必要はない。但し、拠出額の減額は考えても良いと思う。そして減額した分をNISAで運用すれば良い。
- Q結局どんな人がiDeCo加入するべき?
- A
以下3点のいずれかに当てはまる方が加入すべきと考えます。
- 既にNISAで満額の積立を行っていて、毎月の収支が大幅に黒字家計の場合
- 多くの所得税を納めている場合(少なくとも20%(年350万円)が目安と考えます)
- 浪費癖のある方(貯蓄が苦手な方)
逆に、以下3点のいずれかに当てはまる方は加入すべきでないと考えます。
- 課税所得がない場合(拠出時の節税の恩恵が受けられないのなら始める理由がない。NISAで十分。)
- 生活が困窮している又は、生活防衛資金が潤沢にない場合(お金が必要になったとしても最短60歳までは取り崩せないので、始めるべきではないと考えます。)
- 第2号被保険者(割高な厚生年金に加入させられているので、NISAだけで十分であると考えます。元々iDeCoは老齢年金の少ない個人事業主向けの制度でした。)
一応補足程度に紹介します。iDeCoの特徴として前編では触れていなかったのですが、「差押禁止財産」になります。なので、もし仮に自己破産することになったとしても処分されない財産(自由財産)となります。(税金の滞納は差し押さえの対象となり得ます。)
また、勘の良い方なら気づいたかと思いますがiDeCoは課税所得の多い人(高所得者)ほど恩恵が大きく、少ない人(低所得者)ほど恩恵が小さいんです。我が国は累進課税制度を導入しているので、納めている所得税率が高ければ高いほど節税効果が大きく低ければ小さいです。高所得者は老後の資産についてiDeCoに頼らず準備できます。低所得者はiDeCoの恩恵も小さくNISAで準備します。なので、iDeCoの加入率がNISAほど高くないんですよね。。。
- NISA利用意向率:50%以上
- iDeCo加入率:30%以下
ここまでお読みいただきありがとうございます。少しでも参考になれば幸いです。
〜引用〜
NISA利用意向率
iDeCo加入率